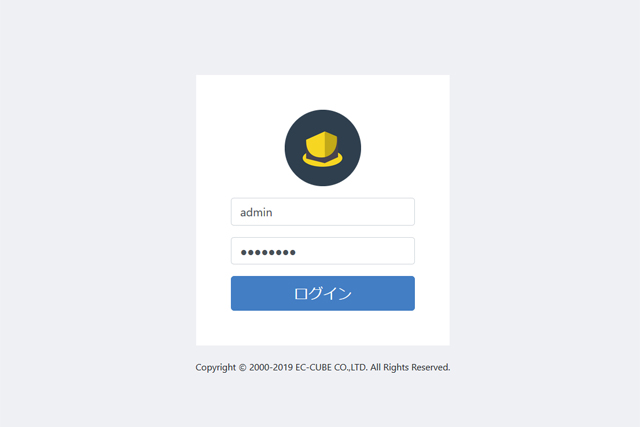月額ボスレンタルサービス「シェアボス」
定額で上司借り放題、そんなサービスが今年開始された。 コンサルタント業「カーマンライン」は9月、デジタル技術に精通した人材を上司として貸し出す「シェアボス」というサービスを開始した。ターゲットは非IT大手企業、ベンチャー企業、投資家で、狙いは経営層のITの知識・経験不足による企業の経営判断(特にIT化)の遅れを解決することである。「ボス」は30~40代が中心で、元エンジニアや元大手企業の執行役員が多く、フリーランスの立場で「シェアボス」に登録し、依頼主の新規事業に関する調査や企画を担う。 このサービスの大きな特徴は、依頼主が何度でも「ボス」を変更できる点である。プランは金額に合わせて大きく3種類、最も大きなプランは月300時間以内の「ボスホ」で1000万円、トライアルとして20万円からのプランも設定されている。 参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000045311.html ─ YODOQの見方─────────────────────────── このサービスが解決できることと、問題点について考えてみた。 解決できること ・非IT大手企業やベンチャー企業のIT化 上記に述べた通り、このサービスの狙いでもある。今日、日本全体として企業のIT化が世界と比較して遅れており、その理由に経営層のITへの関心の低さが挙げられている。若い人材のITへの関心の高さを活かしたり、考えが固まっている企業の新陳代謝を促す役割を果たすのではないかと考える。 ・人間関係の不和による退職などの減少 企業の退職理由のうち、人間関係が1割から2割を占めるというデータもある(参考:厚生労働省 第6回21世紀成年者縦断調査(国民の生活に関する継続調査)結果の概況)。このサービスでは「ボス」が何度でも交代可能であるため、よりよい人間関係を構築し仕事に取り組むことができると考える。 問題点 ・「ボス」の決定を信頼できるか いくら実績のある人材とはいえ、企業にとっては新参者である。そのような「ボス」が企業経営を揺るがすような計画を立てたてたところで、信頼できるのか。 「ボス」の責任について調べたところ、彼らは請負契約であり、基本的に、下した決断に対して責任はとらないようだ(ただし、賃金を上限とした損害賠償責任はある)。しかし、多くの「ボス」が顔出し名前出しをしており、かつ、このサービスは依頼主にとって「ボス」は代替可能であるため、悪評を立てられたらすぐに仕事が減少するだろう。「ボス」も生活が懸かっているからこそ、依頼主もある程度信頼してもいいと見ることもできる。 ・大手戦略コンサルや外部取締役では同様の機能を果たせないか このサービスを機能面で見ると、戦略コンサルや外部取締役と大きくは変わらない。しかし、金額はやや安価である。実際に企業の根幹システムでなくても、企業内に少し新しい風を吹かせたい、ベンチャー企業で資金は少ないがITを活用していきたい、といった企業には需要があるだろう。 最後に、上司の入れ替えサービスが開始された今、部下の入れ替えサービスが開始されてもなんら不思議ではないと感じた。IT化により仕事の機械化が進み、能力のある人材だけが選ばれる世の中になるのかもしれないと感じた。 参考: ・シェアボス公式HP ・中日新聞「定額で上司貸します。東京のコンサル会社が新サービス」2019年11月20日付朝刊 ・FNN PRIME 「月々低額で「上司入れ替え放題」のサービスが日本初登場?!どんなものか聞いてみた」2019年9月19日付